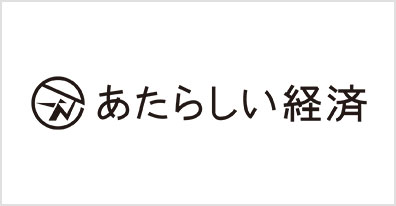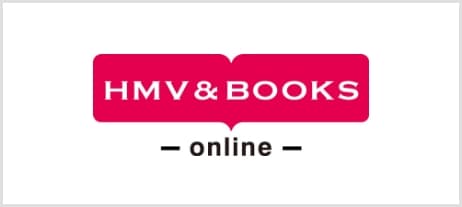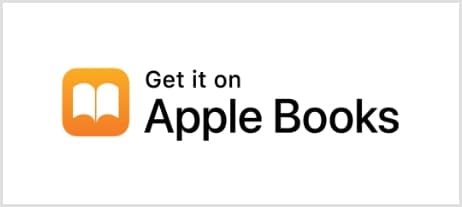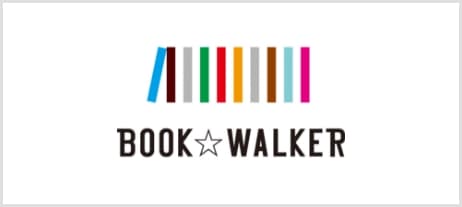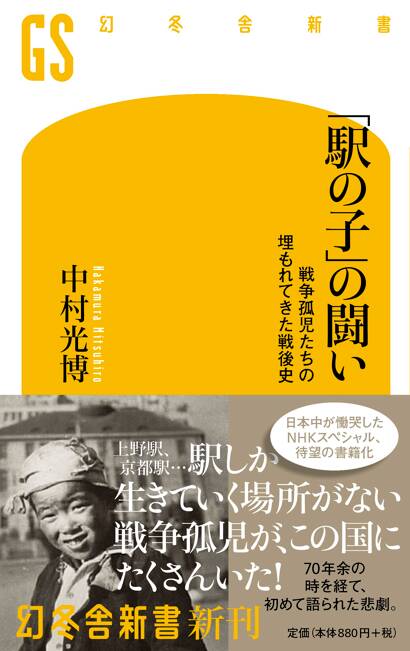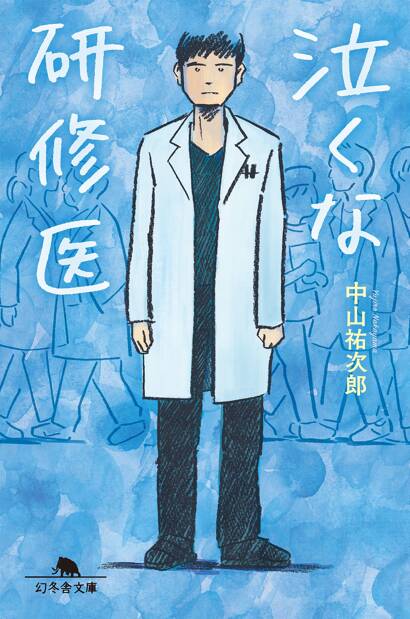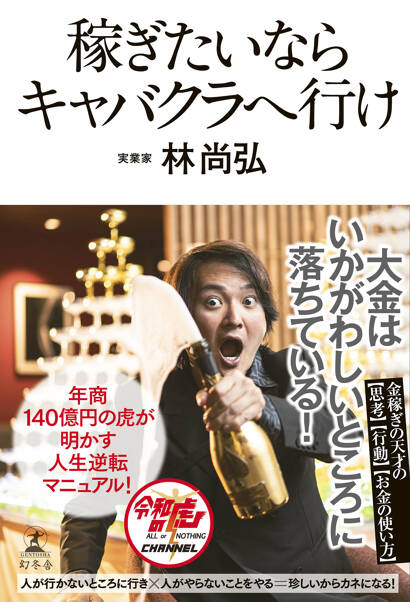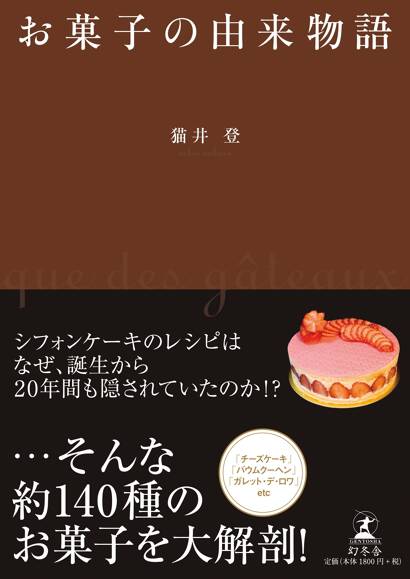給食の謎 日本人の食生活の礎を探る
- 発行形態 :新書
オーディオブック
電子書籍 - ページ数:248ページ
- ISBN:9784344987159
- Cコード:0295
- 判型:新書判
作品紹介
現役の学校栄養士で給食マニアとしても知られる著者があらゆる謎を徹底解説。
昭和の給食を食べていた世代にとって、令和の給食は驚きの連続だ。
なぜ昔は毎日パンだったのに今は週1回程度なのか?
冷たい麺類禁止の地域があるのはどうして?
給食室がある学校は減っている?
ソフト麺はどこに消えた?
ギモンの背景を探るうち、給食が日本人の食生活まで変えたという歴史が如実に浮かび上がってきた。
献立作成の裏側から厳格すぎる衛生管理まで給食トリビアが満載、空腹時は閲覧注意!
目次
はじめに
第1章 ある日の給食室
給食室には校長でも入れない
学校給食の4つの主要方式
自校方式の学校は半数以下
5時半:出勤――衛生管理チェック
始発出勤で得られた、業者からのナマの情報
6時:食材の検収――冷蔵・冷凍品は調味料まで当日使い切る
飲食店をはるかにしのぐ、給食室の厳密な区分け
調理の設計図となる「作業工程表」
6時半:調理開始――前日調理禁止はつらいよ
7時:調理室――美味しい冷凍みかんの作り方
あの有名アイスも給食用がある
切りものを支えるまな板の秘密
給食のサラダは加熱処理している
9時:食器類セッティング――クラス別に数える重労働
「スチコン」が給食を格段に美味しくした
安価なパンに給食室でひと工夫
600食なら320合ものお米を炊く
進化がやまない調理機のエース「回転釜」
11時40分:検食――校長による“毒見”
12時:料理の搬出――廊下でワゴンに目を光らせる
12時10分:給食の時間――児童生徒とのコミュニケーションタイム
13時:残食量の記録――残食ゼロの日は最高に幸せ
13時半:洗浄・消毒――調理しながらの洗い物は禁止
第2章 献立作りの舞台裏
“栄養士の頭のなか”はどうなっているか
今日の献立は、半年前にはほぼできている
献立計画こそ栄養士の醍醐味
1学期ぶんの献立計画が3、4日で完成する
なぜ麺は2週に1~2回しか出ないのか
令和の子どもは昭和のパン給食が「うらやましい」
基準値は1食ごとではなく1か月の平均で満たす
献立作りの難易度はまるでルービックキューブ!
さらに難易度を高める「食缶は各クラス1個」の縛り
豚肉だけで100種類以上もの選択肢がある
白こんにゃくは食物繊維のお助け食材
足りない食品群と栄養素は副菜で補給
給食の出汁はなぜ強火でゴツゴツ煮出すのか
針のムシロ!? 献立構成会議
バズる「給食だより」まで登場
教材として利用できるレベルの献立表が理想
食事内容を充実させることも責務のうち
〈コラム〉 過酷すぎた「2週間揚げパン生活」
第3章 給食、その激動の歴史
時代に翻弄された、日本の学校給食
始まりはお坊さんが出した無料の食事
戦後、アメリカの援助で再開
財政難による存続の危機
脱脂粉乳時代の終焉
待ち望まれた米飯給食の開始
平成の給食は「安全」と「食育」を求めて進化
令和の給食最前線
日本の給食実施率は100%ではない
〈コラム〉ソフト麺はどこに消えた?
第4章 給食を規定するさまざまな基準
献立の根拠となる学校給食法
献立作成者が取得しなければならない資格
栄養バランスや食品構成を定める基準
なぜ給食の飲み物は牛乳なのか?
ルールの地域差を生む一因は食中毒事件
O-157による集団食中毒
食中毒が起きるメカニズムとは
宇宙食レベルの衛生管理
食の安全を可視化する「作業動線図」
唐揚げの工程を4人で分担してリスクを回避
給食で使う野菜は3回洗っている
食中毒、意外な伏兵はシジミやアサリ!
床は衛生的なドライシステムに変わりつつある
食物アレルギーのある子どものための「お手紙」
宗教別の対応食をどう考えるか
特別支援学校・特別支援学級の給食
コロナが激変させた「給食の時間」
食の楽しみが犠牲になっていないか
〈コラム〉こんなに違うよ世界の給食
第5章 給食とお金
予算が足りなくなるのが一番怖い
3月の献立が豪華になりやすいワケ
なぜ給食は1食260円ほどで食べられるのか
カニや神戸牛が給食に!? うらやましい自治体補助
給食費の未納を防ぐ仕組み
セーフティネットとしての役割
給食費の無償化に踏み切る自治体が増加中
納品業者と栄養士の癒着は可能か
大手業者が強い食材、個人商店が強い食材
栄養士が冷や汗をかく発注ミスの恐怖
〈コラム〉江戸東京野菜で挑んだ給食甲子園
第6章 栄養と美味しさのベストバランスを探して
あの手この手で食品摂取量の数値を満たす工夫
緑黄色野菜類――高価だが替えが利かない
その他の野菜類――野菜摂取量を助ける「三種の神器」
芋及び澱粉――献立に入れる余地を常に探している食材
豆類――苦手な子どもの多い、悩みどころ
豆製品類――苦労知らずの“食材の王様”
きのこ類――プリプリ食感を諦め、徹底的に炒める
魚介類――高い固定費と考え、よいものを買う
卵類――一品料理で摂取量を稼ぐ
藻類――忘れていると月末の給食が海藻まみれに
小魚類――アーモンドフィッシュは「副菜」にカウント可能
肉類――少量の加工肉に頼って摂取量を抑える
混ぜ込みづらい栄養素は「鉄」「亜鉛」
「残されない給食」を実現する7つのテクニック
その1:人気メニューの力を借りる
その2:魚料理はお寿司を見習え
その3:子どもの口の大きさを理解する
その4:人参やパプリカを多用して鮮やかに
その5:野菜を残さず食べてもらうドレッシングの工夫
その6:デザートは人気のなさそうな献立の日に入れる
その7:まぜごはんパワーを使う
〈コラム〉 人気ラーメン店レベルの「給食のラーメン」誕生秘話
おわりに
はじめに
給食というのは、誰もがひとこと語りたくなるテーマです。
「ソフト麺を袋の外側から指で板チョコみたいに4等分して、それをひとつずつ汁に入れるのがうちの学校のマナーだった」
「牛乳瓶のフタがはがせなくて苦労した。えっ、君の地元ではパック入りの牛乳だったの?」
「孫の給食献立表に、ナントカって国の、初めて聞いた料理が書いてあって驚いた」
試しに話題を振ってみれば、こんな声がすぐに集まります。日本の給食は明治のなかばに始まり、戦時中の中断を経て、昭和20年代後半には全国の小学校で実施されるようになりました。戦後生まれ以降の世代は、日本で小学校に通った人であれば給食を食べた経験があるというわけです。
誰でも自分の経験を語ることができて、しかも地域差・世代差が存在するという点が、給食の話題が盛り上がる所ゆ え ん 以なのでしょう。
ところが、給食についての正しい情報をお持ちの方は意外なほど少ないのが実情です。
なぜ給食の飲み物は主食がごはんの時でも必ず牛乳なのか?
児童生徒が今日食べる給食の献立は、どれぐらい前に決定しているのか?
たびたびニュースを賑わす「給食費未納問題」や「給食費無償化」は現在、どのような状況にあるのか?
こうした問いにすらすら答えられる方は決して多くありません。
私は東京都文京区の小学校に勤務して15年になる学校栄養士です。圧倒的に女性が多い栄養士の世界では、男性というだけで珍しがられるのですが、さらに私を知る人々が驚くのが(内心引いているのが)、給食にかける異常なまでの情熱です。
給食のラーメンを有名店と遜色ないレベルにするという無謀な目標を掲げて、毎晩店に通って研究したり、給食で使う業務用大型機械を大枚はたいて自宅に設置したり、農家さんの手伝いに半年通いつめて、貴重な野菜を給食用に卸してもらう契約をとりつけたり。
そのうち“給食バカ”などと呼ばれるようになりました。
そして平成25(2013)年、「全国学校給食甲子園」という献立コンテストで男性栄養士として初優勝を果たしたことをきっかけに、メディアや講演会で給食の話をする機会が増えました。すると、給食の話題には誰もが関心を寄せるのに、給食システムの背景や内幕を知る人は、現場の従事者を除くと極端に少ないことに気づいたのです。
給食のことは小学生や中学生の子どもを持つ親御さんだけが知っていればよい、というわけではありません。世界情勢の悪化による物価高が給食の予算を直撃し、SNSを騒がせるほど寂しい献立にならざるを得なかったり、あるいはコロナ禍で「黙食」「前向き給食」「おかわり禁止」が子どもたちに強いられたりと、社会の抱える問題によって給食が脅かされることはままあります。
給食は、その国の大人が子どもたちをどれくらい大切にしているのか、ということの映し鏡であると言えるのです。
本書では、自他ともに認める給食マニアの私が、皆様にぜひ知っていただきたい給食を取り巻く状況について、さまざまな角度から解説していきます。
第1章では、給食室で毎日どんな流れで給食が作られているのか、ある1日の様子をご紹介します。現代の給食室は教職員でも立ち入り禁止、校内でもっとも秘密の場所です。
続く第2章では、学校栄養士がどのようなことを考えながら献立を立案しているのかをご紹介します。月ごとの献立表が配られるのをみんなが楽しみにしていますが、その陰で栄養士は想像を絶する複雑な規定をどうにかこうにかクリアして作成しています。
第3章では、現在へと連なる給食の歴史をいくつかのターニングポイントを軸に解説していきます。給食は日本の戦後復興と軌を一にするように、幾多の問題を乗り越えつつ制度としてだんだんと整えられていきました。
そして第4章では、給食を規定するさまざまな法律や基準についてご紹介します。給食の謎ルールはだいたいここが発端です。非合理的だったり不思議に思えたりするローカルルールの背景には、興味深い理由が隠れているものです。
第5章では給食費の地域差や、予算管理の難しさ、発注ミスの恐怖など、普段なかなか語られることのないお金にまつわる本音をご紹介します。
最後の第6章では、栄養士が子どもたちに必要な栄養素を摂取してもらうために、食べ残しを防ぐどのような工夫をしているのか、そのテクニックを披露します。
給食は未来を担う子どもたちの、食の原体験となるものです。できるだけ好き嫌いをなくして、これからの長い人生における食の楽しみが増えるように、大げさに言えば日本人の食生活が豊かであり続けることを目指して、私たち給食従事者は今日も働いています。
給食にまつわる硬軟織り交ぜたトリビアを網羅した本書で、ぜひ皆様に給食の世界を深く知っていただき、この制度がさらによいものになるよう、議論のきっかけになれば幸甚です。
幻冬舎plusで関連記事を公開中!
著者インタビュー
メディア紹介情報
- 「MONOQLO」2024年11月号「アマゾンオーディブルでラク速インプット!ビジネス書 ドヤれるランキング 会話のネタになりまくり部門」1位
- 日刊ゲンダイ(2024年2月10日号)
- JFN系列ラジオ「レコレール」2024年1月24日放送
- ABCラジオ「おはようパーソナリティ 小縣裕介です」2024年1月24日放送
- TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」2024年1月14日放送
- ダイヤモンド・オンライン
・アレルギー、宗教…学校給食は制約がいっぱい!献立づくりに苦闘する栄養士たち
- FNNプライムオンライン ・昔懐かしの「ソフト麺」の今。給食の定番だったメニューは機械や工場の老朽化により需要が減少
・なぜ給食の飲み物は牛乳なのか。「決められたカルシウム値を補うために必須だった」現役学校栄養士が解説
- 「本の雑誌」2024年2月号
- プレジデントオンライン
・なぜ給食の人気メニュー「ソフト麺」は消えたのか…平成後期に起こった「学校給食の大転換」の意外な背景 - 静岡新聞(2024年1月7日)
- 「GetNavi web」知らなかった!? 給食の意外なルール。学校栄養士が語る給食トリビア満載の一冊~注目の新書紹介~